
波乱の生涯を辿った帝〜平城天皇と「薬子の変」の真相
📜 平城天皇の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 諱(いみな) | 阿保親王(あぼしんのう) |
| 生年 | 773年(宝亀4年) |
| 崩御 | 824年8月5日(弘仁15年)享年52歳 |
| 在位期間 | 806年4月1日 ~ 809年5月18日 |
| 父 | 桓武天皇(第50代天皇) |
| 母 | 藤原乙牟漏(ふじわらのおとむろ) |
| 皇居 | 平城京(奈良) |
| 廟号 | 平城天皇 |
| 年号 | 大同(だいどう) |
桓武天皇の長男として生まれ、若くして皇位を継承した平城天皇。しかし、その治世はわずか3年で終わりを迎え、退位後には朝廷を揺るがす大事件「薬子の変」を引き起こしました。今回は、その波乱に満ちた生涯と、事件の真相に迫ります。
期待された皇太子から、短命政権の帝へ
773年(宝亀4年)に生まれた阿保親王(後の平城天皇)は、桓武天皇の嫡男として、周囲から将来を嘱望されていました。806年、父の崩御を受け、満を持して第51代天皇として即位します。
しかし、在位期間はわずか3年と短いものでした。病弱であったと伝えられる平城天皇は、政治への意欲も薄く、実際の政務は周囲の官僚や貴族に大きく委ねていたようです。
退位後、再び権力への執念を燃やす
809年、平城天皇は病を理由に、弟である嵯峨天皇に皇位を譲ります。退位後、「太上天皇(だいじょうてんのう)」となった平城上皇は、旧都である平城京に戻り、静かに過ごすはずでした。
しかし、彼の心には再び政治の実権を握りたいという強い思いが芽生えます。その中心にいたのが、寵愛する藤原薬子(ふじわらのくすりこ)と、その兄である藤原仲成(ふじわらのなかなり)でした。
藤原薬子は、平城上皇の寵愛を背景に朝廷内で急速に勢力を拡大。兄の藤原仲成も、上皇の信任を得て重要な地位を占めるようになります。平城京は、退位した上皇を中心とした新たな政治的拠点となりつつありました。

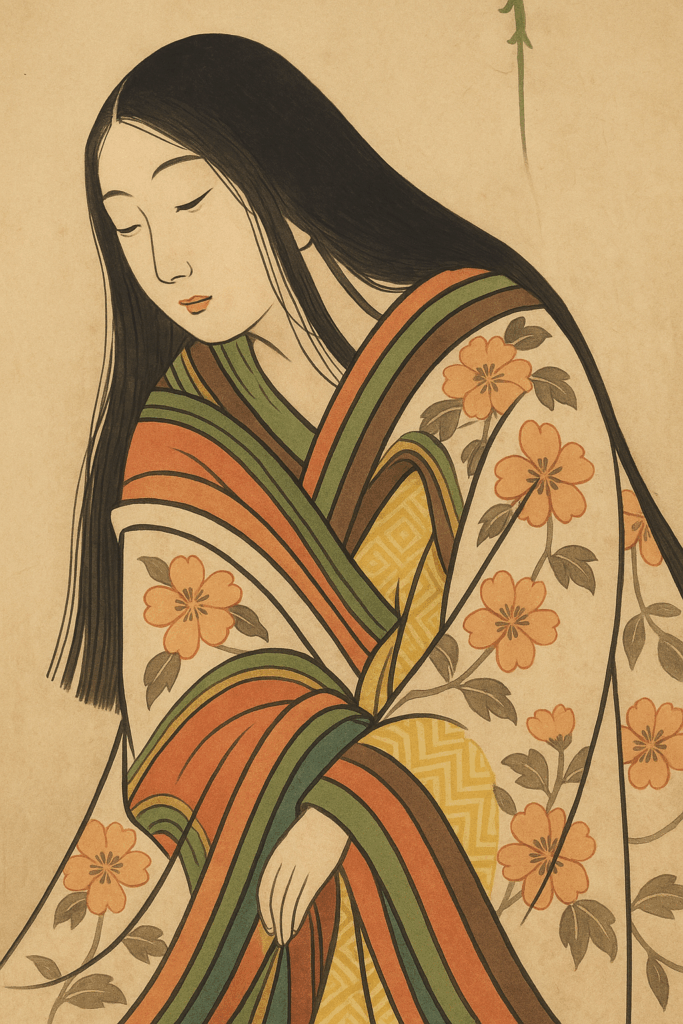
朝廷を二分した「薬子の変」
810年、事態は急展開を迎えます。平城上皇が突如、「都を再び平城京に戻す」と主張し始めたのです。これは、嵯峨天皇が治める平安京に対し、明確な政治的圧力をかける行為でした。
この動きに対し、嵯峨天皇は迅速かつ強硬な措置を取ります。
- 東国へ向かう主要な街道を封鎖し、平城上皇の行動を牽制。
- 側近の坂上広野らに命じ、平城京を包囲。
嵯峨天皇の断固たる態度に、平城上皇は行幸を中止し、事態を収拾するため出家を決意します。しかし、嵯峨天皇は、この一連の騒動の首謀者は藤原薬子と仲成であると断じ、二人を捕らえ処刑。薬子は自害し、平城上皇は失意のうちに仏門に入りました。これが、歴史に名を残す「薬子の変」です。
事件が残した教訓
薬子の変は、退位した上皇といえども、現天皇の権威に逆らうことは許されないという原則を明確に示す出来事となりました。また、嵯峨天皇による迅速な対応は、天皇の権力基盤をより強固なものとし、その後の朝廷体制に大きな影響を与えました。
寵愛と権力への執着が引き起こした悲劇。「薬子の変」は、平城天皇の波乱の生涯を象徴する出来事として、歴史に深く刻まれています
コメントを残す